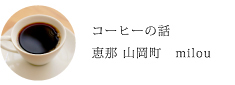僕的取材論(なーんて)。
2010年01月12日(火)

先日、とある印刷物の取材に出かけた。取材対象者は大学生。高校、大学と7年間、同じ競技を続けてきた彼女に、その面白みやそこから得られたものをうかがうつもりだった。いつもは僕ひとりで話をうかがうことが多いのだけど(その方が被取材者はリラックスできるし、話に集中できるから)、その日は広告代理店のディレクターが同席することになっていた。
大学では「それまでやっていなかった新しいこと」や「バイトと掛け持ちできるラクなこと」を始める学生も少なくないが、彼女はより高いレベルに自身を高めたくて、その競技を続けようと思ったと言う。ゆっくりだけど気持ちや考えをまとめ、自分の言葉で話そうとする彼女の姿勢に僕は好感を持ち始めていた。ところが話が核心に近づいてきたころ、ディレクターが「7年続けて、成長したって感じがしますか?」、「試合で戦っているのは、自分自身じゃないですか?」なんて質問をする。おいおい。よしてくれ。
そういう画一的な質問は被取材者が持っているリアルな体験や言葉を隠してしまう。被取材者本人がそれを口にするのはかまわないのだが、それは取材する側が口にするべきではない。
先日、このブログでも紹介した小原玲さんの講演会で、小原さんもおっしゃっていたのだけど、この類の仕事をしていると既存の型にはめようとする傾向が出てくる。以前、報道カメラマンとして活躍されていた小原さんは難民キャンプに行くと、空腹に苦しみお腹を膨らませた子どもを捜してしまったと苦笑されていた。でも僕にはその気持ちがよくわかる。その方がラクチンだし、仕事も早く片付くからだ。しかしながら、それは真実を伝えることとはほど遠い。「難民キャンプ=飢えに苦しむ子ども」という安直なイメージを繰り返しているに過ぎないのだ。
本多勝一氏の著作「事実とは何か?」を引き合いに出すまでもなく、100%の客観はありえない。文章にしろ、写真にしろ、書く者、撮る者の主観が入り込む。だから僕たちは常に立ち位置を意識しなければならない。質問をニュートラルに、フラットにしなければならない。つまらない誘導や押しつけは、あってはならない。
クライアントの意向に沿って制作される広告物に、客観性云々など馬鹿馬鹿しいと笑われるかもしれない。しかし、わざわざ時間を割いて話を聞かせてくれる相手を、こちらの想定したワクに押し込むことは僕は失礼だと思う。一人ひとりの言葉にしっかり耳を傾けたいと思っている。